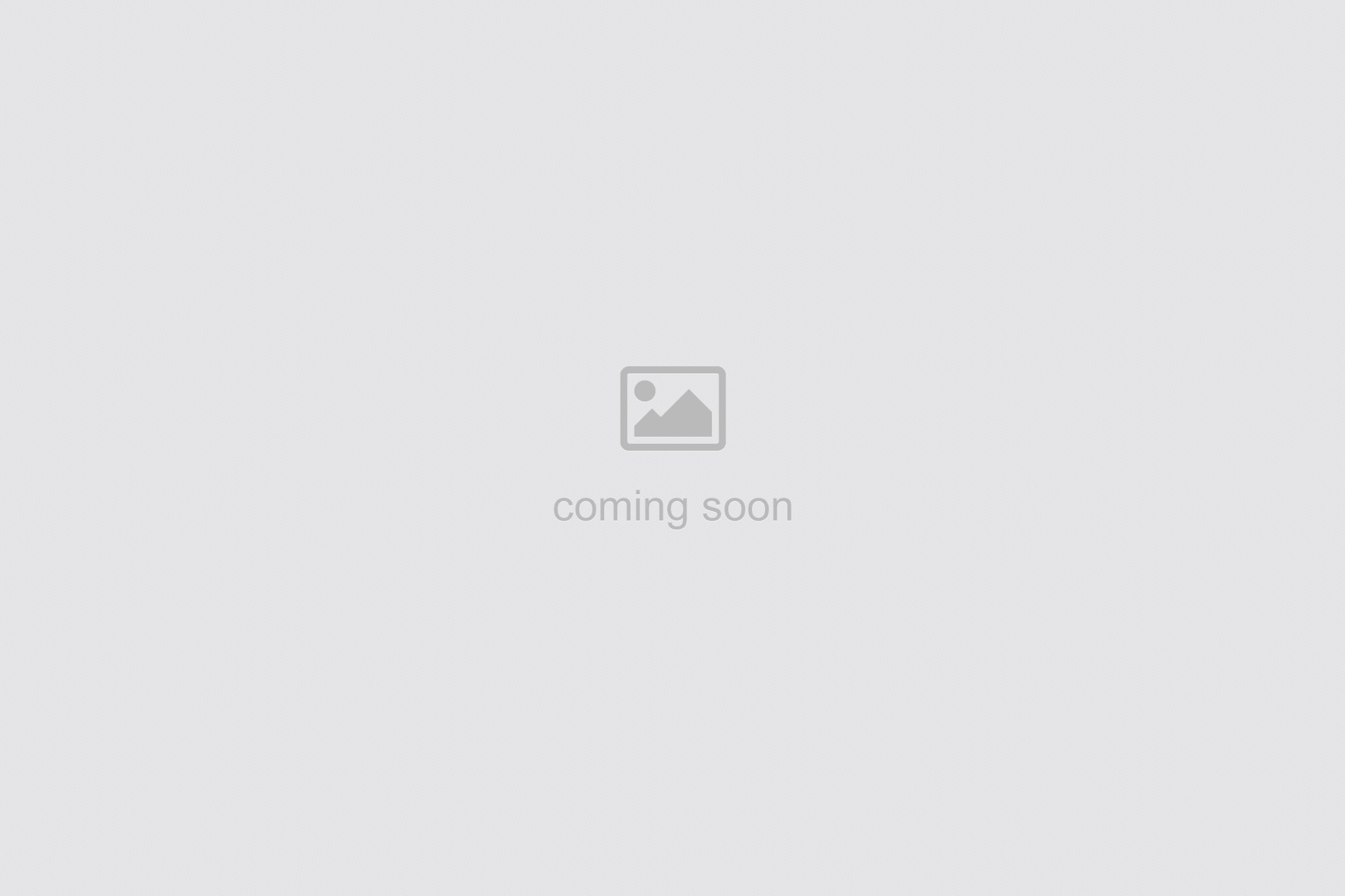ブログを始めました
さー今日から始めよう身近に見られる秋・冬の山野草
2024-12-12
こけ採り名人について歩いたころは、ついていくのが精いっぱいで、野草観察などしたことなかったが、昨年亡くなり一人で歩くようになると、意外といろいろな花が観察できた。
道ばたの草は季節の便りであり、それを眺めながらあるくのは好きだ。
道ばたにどこでも見られるエノコログサ 犬のしっぽのようで、温かみが感じられるものだ。
しかし、よく見ると左は穂が直立して、短めで、小ぶりです。一方 右は背丈も大きく、穂が垂れているのが特徴です。
左がエノコログサ(別名ネコジャラシ)で右がアキノエノコログサです。
--2023.9.21 能登島--
キツネノマゴ
2024-12-13
一見地味ですが、よく観察するととても可愛らしい花を咲かせます。
茎は枝分かれしやや斜めに立ち上がりながら生え、高さは10cm~40cmぐらいで茎先から穂状花序をだし、7mmほどの赤紫色の花を2~3個咲かせます。葉は対生です。
奥ゆかしい花色ですね --10月 城山--
キツネとつく花は他にキツネノボタン、キツネノカミソリなどありますが、キツネがまだ身近に感じられた時につけられたんだろうね
花の真ん中に白い星形の模様が見られますが、これは蜜標といって、昆虫に蜜の場所を示すものです。
花穂には尖った苞が目立ち、茎は4角。
このふさふさと見える小さい苞が孫サイズのキツネの尾に見立てたことよりキツネノマゴとなったとか
オミナエシとオトコエシ
2024-12-14
秋の七草の一つであるオミナエシは万葉集や源氏物語に多くの詠んだ歌が残っています。歴史のあるかわいらしい花ですね
繊細で清楚な花姿が秋の野に揺れる様はどことなく儚げに見えます。
一方 右のオトコエシはオミナエシとよく似ていますが、花の色が白い点が大きく異なります。
また、オミナエシに比べて 茎がより太く、葉がより厚いことなど、全体的に逞しい印象です。
ニラ(ユリ科)
2024-12-15
ベニバナボロギク と ダンドボロギク (キク科)
2024-12-16
ベニバナボロギクもダンドウボロギクも舌状花はなく、よく似ていますが、ダンドウボロギクの頭花は淡黄色で上を向き、葉は線形で長く、無柄です。
ベニバナボロギクはオレンジ色で下向き、葉は倒卵状長楕円形で頭大羽状に中裂し、短柄があります。
葉の匂いはベニバナボロギクの方が春菊のような香りがして好きですが、ダンドウボロギクの若葉は食用になります。