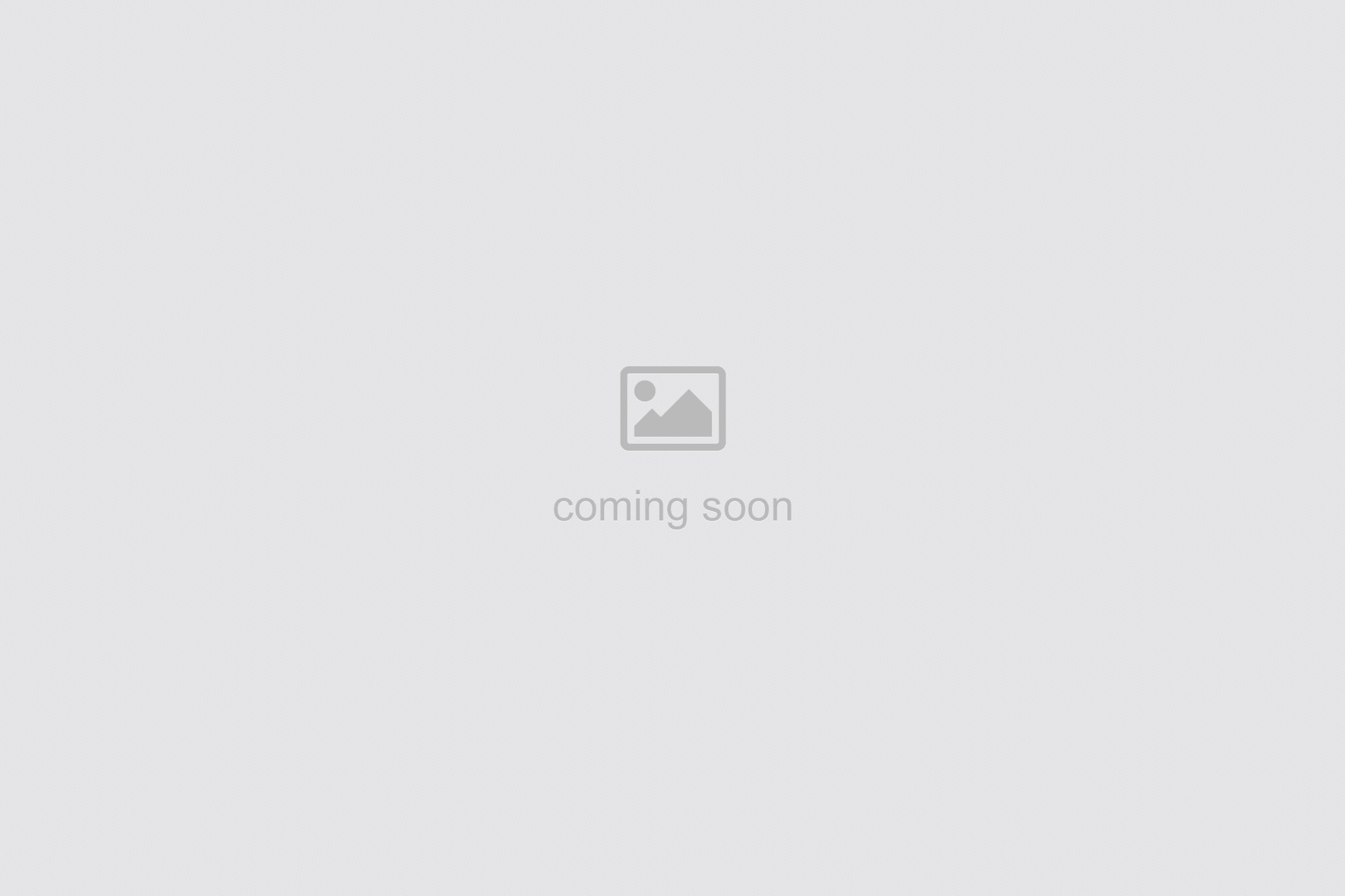ブログを始めました
今日から風薫る5月 風に吹かれて あてどもなく歩きたいものだ
2025-05-01
ツツジは花期が4月から5月で、サツキは5月がら6月で今はまだ花が出てきていません
ツツジとキリシマツツジとの違いは写真のようにツツジは花開いたものと蕾のものとがあり順次開きますが、キリシマツツジはみな一斉に花開き葉が見えないくらいに花が密集して咲きます。
また、雄しべの数がツツジは5本以上でバラバラですが、キリシマツツジはすべてきちんと5本でした。
赤蔵山 幾保比城跡探索
2025-05-04
二度のチャレンジともに失敗 1回目は谷底に入り込み沢沿いの藪漕ぎルート 2回目は藪漕ぎは少しだが崖の激下りルート
二度とも能登島ワラビ採りの後のチャレンジ
国分氏の”城山だより” 毎回楽しみに拝見している。先日の”だより”に幾保比城跡について触れてあった。私も前々から気になっていたとこで、
昨年も一回チャレンジしたが、もっと手前から大外まわりで下りてきた。這う這うの体で もう二度と行きたくないと思っていた。
今回は・151ピークのあたりが城跡で下の寺の裏辺りに出てくると記してあったので、GPSだよりにきっと歩きやすいルートがあると思ったが、二度とも失敗。情けない
でも何とか下りれました。
1回目左のGPSの軌跡は・151を通過していない。最後は谷底に下り、この標高差なら谷底でも大丈夫と思い沢に入った。倒木と藪漕ぎの連続で大変だった。
本日2度目のチャレンジ。何とか城跡のあった所と思われる・151ピークにたどり着けたが、そこから下るルートがわからず、結局木につかまりながら激下りで下りた。 しかし、不思議なことに最後は1回目と同じところに出てきた。よく理解できなかった。
また、チャレンジの機会が与えられたのかな。 多分 赤線で書いたように下りなければならないのかなと思う。
5月の晴れ渡ったいい日であった。
ふと上を見上げれば
2025-05-03
ワラビ採りの場所は昔の隠し田の跡で よくこんな所に作っていたものだと感心させられます。苦労したんですね その周りの情景です。
ワラビ採りに夢中になっていたが、ふと上を見上げると、ウワミズザクラ、ヤマトアオダモの白い花を咲かせた木々が見られた。
それを眺めて休憩時間が長くなりました。
幾保比城跡探索 その3.
2025-05-04
幾保比城跡探索 その3.
今回は寺の方からの登りを試みたが、登り口がわからず、これまでで一番難儀したルートをとったようで尾根へ出るまでGPSだよりだった。行ったり来たり少し登ってみては下ったり、と今回も正規のルートではなかったようだ。
前回はどこを歩いているのかさっぱりわからず、城跡の全容が全くわからなかったが、今回は大体その全容がつかめた。
幾保比城跡は・151ピークよりやや南に位置し、その周り一周を横堀とし立派な塁線土塁(赤色に囲まれているところ)を巡らせてあった。
城跡の場所(➡ 赤色矢印)はかなり大きなものだった。
城跡は赤蔵山からは南東へ延びる尾根続きのため、かなり大きな堀切二条(ー橙色)で尾根続きを遮断し、また竪堀も数か所あった。虎口(連続虎口)も複雑で防御システムはかなりのハイレベルのものだったと思われる。
北東の尾根にも堀切が二条あった。搦手虎口(裏口)は単純な平虎口で前回はそこから下ったようだ。下った尾根には堀切がなく、ここから山麓と連絡していたのであろう。前回の下ったルートは一概に間違いでなかったのかもしれない。裏口側は表口側の立派な防御システムとはかけ離れたつたない縄張りであるのが不思議だが、長年の月日で崩壊したのかもしれない。
急であったが今回のルートよりましであった。
尾根に上がった後、赤線のルートを見に もう一度チャレンジしないと完結しないようだ。(^^♪
写真は明日に